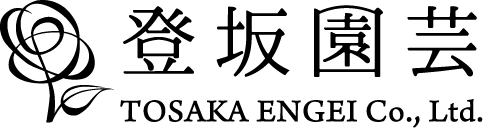また、花が届いた。
社会人3年目、東京での一人暮らしもだいぶ慣れてきた息子からだ。大腿骨骨折のリハビリも乗り越え元気に退院できたとは言え、少し歩きづらそうな恰好で、アジサイを抱えな
がら玄関で水をあげている。花が大きくて、鉢が小さいため、玄関で水をあげて夕方帰宅すると風で倒されていることも多いこの花を妻は昨年末、玄関でつまずき入院した自分になぞらえているようで、今朝も倒れないようにしっかりと固定して出かけて行った。
そういえば、年末のシクラメンも届いた時のような華やかさはないものの、今も軒下で毎日少しずつ花を咲かせており、妻はその花を摘んでは食卓の花瓶へさしている。
あじさいは、良い。手間がかからない、枯れた花を取る必要もない。水の心配だけだが、それは妻が毎日のように、ながめては「今日はこんな天気だから、夕方で良いか?」なん
て言いながら楽しんでいる。

つまらない花である、生きているのだからもっと枯れたり、花が落ちたりすれば、私の出番もあるものの、そんな気配すらない。最近は、あることさえ忘れてしまいそうである。
「妻や息子にとって、私もそう思われているのであろうか?」
定年退職して以来、なんだか日々のやりがいが見つけ出せない。この散歩だってそうである、暇だから何となく。その何となくの日々が早くも1年近く経とうとしている。いつの間にか、真っ青だったアジサイの花は、緑と青の入り混じった不思議な色になっていた。
学生の頃、テスト前に「勉強なんかしてないよ」と言ってはいつも上位の成績だった自分を思い出す。本当は、一生懸命、勉強していた。アジサイだって、何も変化していないよ
うでこうして努力していたのである。
「おまえも、がんばれよ」とあじさいに応援されていた。
つづく
この物語はフィクションです。
文・三石ころ
絵・星野博美