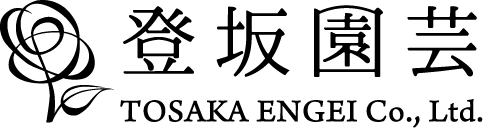花が届いた
社会人3年目、東京で一人暮らしをしている息子からだ。妻が嬉しそうに電話で話している。私といえば、花より団子の精神で、これまで妻に一度も花なんて贈った事はない。電話を終えると、「母さんは花が好きだし、父さんはラーメンが好きだからちょうど良いだろ、【粛らーめん】だって。」と楽しそうに話していた。「なんだそりゃ」と思いながらも、ちょっと太り気味の私の事も少しは気にかけてくれているらしい。
「大腿骨骨折だって」電話越しに元気なく伝える妻、あの日から5日、妻のいない生活、ようやく電子レンジと洗濯機の使い方にも慣れてきた。コーヒーを淹れ、窓辺を見ると見る影もない萎れたシクラメンがあった。これはまずい、妻が毎日ながめては「きれいだね」と言っていたのを思い出す。妻に電話して相談しようかとも思ったが、入院してからの3日間、毎日のように電話して妻に呆れられた記憶がよみがえる。自分で何とかするしかないと思い立ち、妻が行っていたことを思い返す。
そうだ、玄関で風呂桶を使いながら水を与えていたなと思い立ち、早速やってみる。風呂桶半分の水を「どばー」とかけてみる。変化なし。そう簡単には復活しないかと、気持ちを切り替え、近くの本屋へ。栽培実用書はたくさんありすぎて何を読めば良いのかわからず、途方に暮れる。
気分転換に少し遠回りをして帰ると、先ほどまで萎れていたシクラメンが少し元気になったようだ。もう少し様子を見よう。夕飯の買い物を終え、帰宅したころにはシクラメンはすっかり元気になっていた。鉢を持ち上げると、朝よりもだいぶ重たい、水をしっかり吸ったのであろう。でも何かが違う。枯れた花や葉がたくさんあるのである、妻がやっていたように枯れた花を引っ張ってみる。「プチッ」という音とともに簡単に取れた。「プチッ、プチッ、プチッ・・・・」無心になって抜いているときれいな花まで抜いていた。しまった。

翌朝、抜いてしまったきれいな花を妻に届けた、といってもコロナ禍で病室まで行くことはできず、病院の受付に預けただけではあるが。
夕方、「お墓参りじゃないんだから、新聞紙で包んだ花なんて、でもありがとうね。」と少し笑いながら妻からの電話。レース越しのカーテンの光を浴びながら、少しうつむきがちの花が「おつかれさま」と言ってくれているようであった。
この物語はフィクションです。
文・三石ころ
絵・星野博美